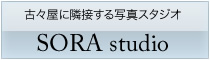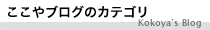2024年7月 月 火 水 木 金 土 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
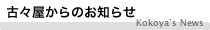
- 2024年6月22日
みらい長崎ココウォークにて浴衣着付けレッスン行います - 2014年10月6日
おはようございます^^ - 2014年10月4日
10月イベント アンティークフェア開催のお知らせ☆ - 2014年9月27日
9月、10月の店休日のお知らせ - 2014年9月13日
9月の店休日のお知らせ
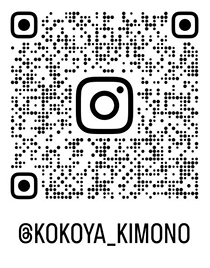
Line